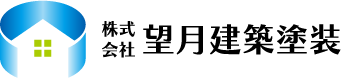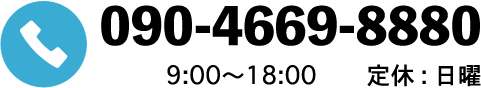本日は、屋根塗装を行う前の現地調査を行いましたのでブログを🆙していきます!!
目次
屋根の種類により塗装できる屋根・できない屋根がある
屋根塗装ができる屋根とできない屋根があります。これは屋根材の種類や劣化状況によって異なります。
塗装が可能な屋根材
一般的に塗装でメンテナンスを行うことができる屋根材は以下の通りです。
- スレート屋根(コロニアル、カラーベストなど):
- セメントと繊維質を混ぜて作られた薄い板状の屋根材で、現在の日本の住宅で最も普及しています。
- 工場出荷時に塗装されていますが、経年により塗膜が劣化し、色褪せ、コケやカビの発生、ひび割れなどが起こります。
- 塗装することで防水性や美観を維持・回復させることができます。
- セメント瓦・モニエル瓦:
- セメントやコンクリートを主原料とした瓦です。
- モニエル瓦は、表面に「着色スラリー」という着色層と、その上にクリアー塗料が塗布されています。
- これらの瓦自体には防水性がほとんどないため、塗装によって防水機能を持たせています。
- 特にモニエル瓦は、塗装前に特殊な高圧洗浄で着色スラリーをしっかりと除去する必要があります。
- 金属屋根(トタン、ガルバリウム鋼板、折半屋根など):
- 軽量で耐久性が高いのが特徴です。
- 塗装することで錆の発生を防ぎ、美観を保ちます。
- 特に遮熱塗料などを塗ることで、夏場の室温上昇を抑える効果も期待できます。
- ただし、ガルバリウム鋼板の中には、耐久性の高い塗膜が施されており、メーカー保証期間が長く、塗装が不要または長期間不要なものもあります(例:ジンカリウム鋼板は石粒で表面を仕上げているため塗装不要)。

ノンアスベストの屋根材は塗装ができない?
- 塗装ができない・推奨されない屋根材
一部の屋根材は、その材質や特性上、塗装ができない、または塗装が推奨されない場合があります。無理に塗装すると、かえって劣化を早めたり、不具合を引き起こす可能性があります。
特に、1990年代後半~2000年代前半に製造されたノンアスベストスレート屋根材には、塗装ができない、あるいは推奨されないものが多く存在します。これは、アスベストが使用できなくなった代わりに開発された初期のノンアスベスト材が、耐久性に問題を抱えているケースが多いためです。
具体的な例としては以下のものが挙げられます。 - パミール(ニチハ製品):
- ミルフィーユのように層状に剥がれてくる「層間剥離」という劣化現象が特徴です。塗装しても下地ごと剥がれてしまうため、塗装はできません。
- コロニアルNEO(クボタ製品):
- ひび割れや欠け、変色が目立ちやすいとされています。
- レサス、シルバス(KMEW / 旧松下電工製品):
- 反り、ひび割れ、剥がれ、欠落などが起こりやすいとされています。
- セキスイかわらU(積水製品):
- U字型の特殊な形状をしており、ノンアスベスト製品は劣化が早く、ひび割れが多いとされています。塗装しても根本的な解決にはなりません。
- アーバニーグラッサ(クボタ製品):
- 鱗のように入り組んだデザインで、細かなひび割れや欠損が発生しやすい特徴があります。
これらの屋根材は、塗装によるメンテナンスではなく、葺き替え(屋根材をすべて新しいものに交換)やカバー工法(既存の屋根材の上に新しい屋根材を重ねて張る)といった方法でのメンテナンスが推奨されます。
そもそも塗装が不要な屋根材
一部の屋根材は、性質上、塗装メンテナンスが不要です。 - 粘土瓦(日本瓦、陶器瓦、いぶし瓦など):
- 粘土を高温で焼き固めて作られているため、瓦自体に高い耐久性と防水性があります。塗装する必要がありません。
- 塗装しても塗料が密着しにくく、剥がれやすいという問題もあります。
- メンテナンスとしては、瓦のズレや割れの補修、漆喰の詰め直し、棟の取り直しなどが行われます。
- 銅板屋根:
- 自然に酸化して形成される「緑青(ろくしょう)」が保護層となり、防錆効果を発揮します。塗装は基本的に行いません。
- ジンカリウム鋼板(石粒付ガルバリウム鋼板):
- ガルバリウム鋼板の表面に天然石のチップを高温で焼き付けているため、塗膜の色褪せがなく、塗装が不要です。
- 製品によってはメーカーから長期の色褪せ・穴あき保証が提供されています。
- アスファルトシングル:
- ガラス繊維基材にアスファルトを浸透させ、表面に石粒を施したシート状の屋根材です。
- 塗装はできますが、アスファルトシングルの特性を考慮した専用塗料を選ぶ必要があります。一般的には塗装よりも部分補修やカバー工法が検討されることが多いです。
劣化状況による塗装の可否
たとえ塗装が可能な屋根材であっても、劣化が著しく進行している場合は塗装ができません。 - ひび割れや欠損が広範囲に及んでいる場合: 塗装だけでは根本的な解決にならず、すぐに不具合が出る可能性があります。
- 屋根材の反りや浮きがひどい場合: 塗料が密着せず、剥がれやすくなります。
- 下地まで腐食が進んでいる場合: 塗装では対応できず、屋根材の交換や下地の補修が必要になります。
重要なポイント - 専門家による診断: 自分の家の屋根材が塗装できるタイプなのか、劣化状況はどうなのかを正確に判断するには、専門家による現地診断が不可欠です。見た目では判断が難しい屋根材も多いため、複数の業者に診断を依頼し、意見を聞くことをおすすめします。


塗装ができない屋根に無理に塗装をするとどうなるか?
塗装できない屋根材に無理に塗装すると、様々な問題が発生し、かえって屋根の劣化を早めたり、費用が無駄になったりする可能性があります。
塗装した場合に起こる主な問題
主に、1990年代後半から2010年頃に製造されたノンアスベストスレート屋根材の一部が、塗装できない、または塗装に不向きとされています。これは、アスベストの使用が禁止された後、急遽代替品として製造されたため、耐久性や性質に問題がある場合があるためです。
- ひび割れ、塗膜の剥がれ: ノンアスベストに切り替わった時期の製品は、ひび割れやすく、塗装しても塗膜が剥がれやすいです。
なぜ塗装できないのか?
これらの屋根材が塗装できない主な理由は以下の通りです。 - 屋根材自体の強度が弱い: ノンアスベストに切り替わった時期の製品は、アスベストを含まないことで強度が低下しているものがあり、塗装の負荷や経年劣化に耐えられません。
- 素材の性質に合わない: 塗料が屋根材の表面にしっかり密着しない、あるいは塗装の乾燥による収縮で屋根材自体が破損してしまうなどの問題があります。
- 劣化が進行している: 塗装できない屋根材は、すでにひび割れや剥がれが進行していることが多く、その上から塗装しても根本的な解決にはなりません。
塗装してしまったらどうなるか - 早期の劣化: 塗装直後はきれいになりますが、早ければ2~3年で塗膜が剥がれたり、屋根材自体がひび割れたり、欠けたりします。
- 費用の無駄: 高額な費用をかけて塗装しても、すぐに再劣化してしまうため、結果的に無駄な出費となります。
- 雨漏りのリスク: 劣化した屋根材の上に塗装することで、かえって排水性が悪くなり、雨漏りの原因となる可能性もあります。
- 屋根材の破損: 脆い屋根材の上で塗装作業を行うことで、職人が歩くだけで屋根材が割れてしまうリスクもあります。割れた屋根材が強風で飛散し、周囲に被害を与える可能性も考えられます。
適切なメンテナンス方法
塗装できない屋根材の場合、塗装は推奨されません。代わりに以下の方法が検討されます。 - 屋根カバー工法: 既存の屋根材の上に新しい屋根材を重ねて設置する方法です。既存の屋根材を撤去する手間がないため、工期や費用を抑えられる場合があります。
- 屋根葺き替え工事: 既存の屋根材をすべて撤去し、新しい屋根材に交換する方法です。費用はかかりますが、下地の状態も確認・補修できるため、根本的な解決になります。

外壁診断士を保有しているスタッフがお伺いさせて頂き、お建物の劣化状況や塗装ができる素材かどうか判断をして適切なご提案をさせて頂きます!!
株式会社望月建築塗装では、はしごを使用して目でみてしっかりと判断をさせて頂きます。
塗装のことならお任せ!!東京都・山梨県・埼玉県・神奈川県と羽村市を中心に屋根・外壁塗装工事を行わせて頂いておりますのでお気軽にお問合せ下さい!!