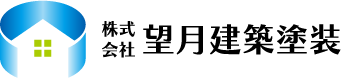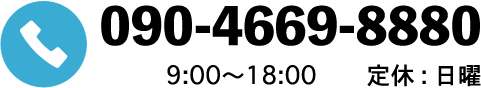本日は、東京都にて外壁塗装工事を行わせて頂いたM様邸のご紹介をさせて頂きます!!
この度は、弊社にお問合せ頂き、ご用命頂き有難う御座いました!!
工程を順番にご紹介させて頂きますのでぜひご参考に見てみてください!!
外壁塗装前の高圧洗浄


外壁塗装を行う前には、高圧洗浄が非常に重要な工程
単なる汚れ落としではなく、塗装の仕上がりや耐久性を大きく左右する役割があります。
高圧洗浄の目的と必要性
高圧洗浄の主な目的は以下の通りです。
- 塗料の密着性向上: 外壁には、長年の間に蓄積されたカビ、コケ、藻、ホコリ、排気ガス、雨だれ、さらには劣化して粉状になった旧塗膜(チョーキング現象)などが付着しています。これらの汚れや劣化した塗膜が残ったままだと、新しい塗料がしっかりと外壁に密着せず、早期の剥がれやひび割れの原因となります。高圧洗浄によってこれらの不純物を徹底的に除去することで、塗料が外壁にしっかりと定着し、本来の性能を最大限に発揮できるようになります。
- 美しい仕上がりの実現: 汚れや劣化した塗膜を取り除くことで、外壁の表面が滑らかになり、塗料が均一に塗布されます。これにより、ムラのない美しい仕上がりを実現できます。
- 外壁の寿命を延ばす: 塗料がしっかり密着することで、外壁を保護する効果が高まり、塗装の寿命を延ばすことができます。
- 下地の状態確認: 高圧洗浄によって古い塗膜や汚れが取り除かれることで、普段は見えにくい外壁のひび割れ(クラック)や浮き、シーリング材の劣化状態などを発見しやすくなります。これにより、塗装前の適切な下地補修を行うことができます。
高圧洗浄のメリット - 塗料の性能を最大限に引き出す: 密着性が高まることで、塗料が持つ防水性、耐候性、防汚性などの機能が十分に発揮されます。
- 塗装の耐久性向上: 剥がれやひび割れのリスクが減り、塗装が長持ちします。
- 仕上がりの美しさ: 均一な塗膜形成により、見た目が格段に向上します。
高圧洗浄のデメリット・注意点 - 水圧による影響:
- 外壁材や塗膜の損傷: 家庭用の高圧洗浄機と異なり、プロが使用する高圧洗浄機は水圧が強力です。誤った使い方や水圧調整を誤ると、外壁材を傷つけたり、劣化している塗膜を過度に剥がしてしまう可能性があります。特に、モルタルや劣化したサイディングボードなどは注意が必要です。
- シーリング(コーキング)の破損: 目地のシーリング材に直接強い水圧を当てると、破損につながることがあります。
- 住宅内部への水の浸入: 窓や換気口などがしっかり閉まっていないと、水が室内に浸入する可能性があります。
- 近隣への配慮: 洗浄水や汚れが周囲に飛び散る可能性があるため、事前に近隣への挨拶や養生(シートで保護)が重要です。
- 作業中の制限: 高圧洗浄中は、窓を開けられなかったり、洗濯物を外に干せなかったりすることがあります。
- 乾燥時間が必要: 高圧洗浄後、外壁が完全に乾燥するまで塗装作業はできません。通常、24時間から48時間程度の乾燥時間が必要です。
バイオ洗浄について

乾燥後、外壁塗装工事


外壁塗装2回塗り
外壁塗装における「下塗り二回塗り」は、通常の塗装工程では一度で済ませることが多い下塗り工程を、あえて二度行うことを指します。この方法は、特定の状況や目的において非常に有効であり、塗装の品質と耐久性を大きく向上させるメリットがあります。
下塗りの役割と重要性
まず、下塗りがなぜ重要なのかを理解しておく必要があります。下塗りは、外壁塗装において「接着剤」のような役割を果たす塗料です。主な役割は以下の通りです。
- 密着性の向上: 上塗り塗料と外壁材(下地)の密着性を高め、剥がれやひび割れを防ぎます。
- 吸い込みムラの防止: 外壁材の吸水性を均一にし、上塗り塗料が不均一に吸い込まれることで起こる色ムラを防ぎます。
- 下地の補強・調整: 劣化した下地を補強し、上塗り塗料の性能を最大限に引き出すための土台を整えます。
- 旧塗膜の影響抑制: 旧塗膜の色やアクが上塗り塗料に影響するのを防ぎます。
下塗り二回塗りの目的とメリット
通常は一度で十分な下塗りですが、二回塗りをすることで、以下のような目的とメリットが得られます。 - 密着性のさらなる強化:
- 特に吸い込みが激しい下地(例:モルタル、劣化したサイディング、チョーキングがひどい外壁など)の場合、一度の下塗りでは塗料が十分に吸い込まれてしまい、表面に残る塗膜が薄く、接着力が不足することがあります。二回塗ることで、下地にしっかりと浸透し、かつ表面にも適度な塗膜を形成できるため、上塗り塗料との密着性を格段に向上させます。
- 旧塗膜が大きく劣化している場合も、一層目の下塗りが劣化部分を固め、二層目で密着性をさらに高める効果が期待できます。
- 吸い込みムラの完全防止:
- 下地の吸い込みが不均一な場合、一度の下塗りでは完全に吸い込みを抑えきれないことがあります。二回塗ることで、下地の吸い込みを完全にコントロールし、上塗り後の色ムラを徹底的に防ぎ、均一で美しい仕上がりを実現します。
- 上塗り塗料の性能を最大限に引き出す:
- 下地がしっかりと整うことで、上塗り塗料本来の性能(耐久性、防水性、低汚染性など)が十分に発揮されます。下地の吸い込みが激しいと、上塗り塗料の顔料や樹脂が下地に吸い込まれてしまい、塗料の持つ機能が十分に発揮されないことがあります。二回塗りで吸い込みを抑えることで、上塗り塗料が塗膜としてしっかり機能するようになります。
- 塗膜の厚みと耐久性の向上:
- 下塗り層が厚くなることで、全体的な塗膜の厚みが増し、外壁の保護性能が向上します。これは、長期的な耐久性につながります。
下塗り二回塗りが推奨されるケース
以下のような状況では、下塗り二回塗りを検討する価値があります。 - チョーキング(粉吹き)が激しい外壁: 塗膜の劣化がひどく、触ると白い粉が大量に付着する場合。
- 旧塗膜が剥がれかけている・ひび割れが多い外壁: 下地の状態が非常に悪い場合。
- 吸い込みが激しい素材の外壁: モルタル壁や、経年劣化で吸水性が高まった窯業系サイディングなど。
- 淡い色から濃い色へ、または濃い色から淡い色へ大きく色を変える場合: 旧塗膜の色が透けるのを防ぐ効果もあります。
- 費用よりも品質・耐久性を重視する場合: 塗装業者に「長く持たせたい」「最高の仕上がりを求める」と伝える場合。
注意点と業者選び - 費用増加: 当然ながら、塗料の使用量と作業工数が増えるため、費用は一度塗りに比べて高くなります。
- 適切な判断: すべての外壁で二回塗りが必須というわけではありません。下地の状態や使用する塗料の種類によって、一度塗りで十分な場合もあります。信頼できる業者であれば、下地の状態を正確に診断し、最適な塗装プラン(下塗りの回数を含む)を提案してくれます。
- 乾燥時間の確保: 下塗りを二回行う場合、一層目が完全に乾燥してから二層目を塗る必要があります。これにより、工程が増え、全体的な工期も長くなる可能性があります。
外壁塗装中塗り


なぜ塗装は三回塗りが基本なのか?
- 下塗り(プライマー・シーラーなど):
- 目的:下地と上塗り塗料の密着性を高める。下地の吸い込みを抑える。下地の補強。
- 役割:接着剤のような役割。
- 中塗り(メインの塗料):
- 目的:上塗り塗料の性能を発揮させるための下地作り。塗膜の厚みを確保し、耐久性を高める。色ムラを防ぐ。
- 役割:最終的な色や機能性を持たせる塗料の「一層目」。
- 上塗り(メインの塗料):
- 目的:中塗りの上に重ねて塗ることで、塗膜の厚みを確保し、色や機能性を完成させる。最終的な美観を整える。
- 役割:最終的な色や機能性を持たせる塗料の「二層目」。
中塗りの役割と重要性
中塗りは、上塗りと同じ「メインの塗料(仕上げ材)」を使用します。つまり、中塗りと上塗りは同じ種類の塗料を重ねて塗るのが一般的です。その具体的な役割と重要性は以下の通りです。 - 塗膜の厚みの確保:
- 塗料は、メーカーが推奨する「塗膜の厚み」を確保することで、初めて本来の性能(耐久性、防水性、低汚染性、耐候性など)を発揮します。
- 一度の塗装では十分な厚みが得られないため、中塗りと上塗りの2回に分けて塗ることで、適切な塗膜の厚みを確保します。
- 色ムラの防止と均一な仕上がり:
- 下塗りだけでは、下地の吸い込みのムラや、旧塗膜の色の影響が完全に消えない場合があります。
- 中塗りを施すことで、下地の色を完全に隠蔽し、均一な「色の下地」を作ります。これにより、上塗りを行った際に色ムラが発生するのを防ぎ、美しい仕上がりを実現します。
- 発色の向上:
- 塗料本来の色を最大限に引き出すためには、十分な塗膜の厚みが必要です。中塗りでしっかりと色を付けることで、上塗りでより鮮やかで深みのある発色が得られます。
- 耐久性の向上:
- 塗膜が二層になることで、紫外線や雨風などの外部からの影響に対する保護性能が高まります。これにより、塗装全体の耐久性が向上し、長期間にわたって外壁を保護します。
中塗り工程の注意点 - 乾燥時間の厳守: 中塗りが完全に乾燥してから上塗りを行うことが非常に重要です。乾燥が不十分なまま上塗りを行うと、塗料が密着せず、剥がれやひび割れの原因となったり、塗膜の性能が十分に発揮されなかったりする可能性があります。季節や天候によって乾燥時間は異なりますが、一般的には数時間〜1日程度必要です。
- 適切な塗布量: 塗料メーカーが指定する塗布量を守って塗ることが大切です。少なすぎると塗膜の厚みが不足し、多すぎると垂れや乾燥不良の原因になります。
- 塗り残し・ムラの確認: 熟練した職人であれば、塗り残しや色ムラがないかを確認しながら丁寧に作業を進めます。
「中塗り省略」や「2回塗り」への注意
一部の業者やDIYで、コスト削減や工期短縮のために「2回塗り(下塗り+上塗り)」で済ませようとすることがありますが、これは基本的に推奨されません。 - 3回塗りの重要性: 多くの塗料メーカーは、塗料の性能を最大限に発揮させるために「3回塗り」を標準工程として推奨しています。
- 性能低下のリスク: 中塗りを省略すると、塗膜の厚みが不足し、耐久性や防水性、美観などが著しく低下する可能性があります。結果として、早期の塗り直しが必要になり、かえってコストがかかることになります。
信頼できる塗装業者は、中塗りを確実に実施し、適切な乾燥時間を確保した上で、上塗りへと進めます。見積もり内容に「下塗り」「中塗り」「上塗り」の記載があるか、使用する塗料の種類とともに確認することが大切です。


綺麗に仕上がりました!!今回2階と1階で仕様が違う為、ご紹介させて頂きます。


すみません、、、今回1階の施工写真を撮り忘れてしまいました(>_<)
なのでこちらの写真だけになりますがご紹介させて頂きます。
こちらは、外壁塗装完了後に、シーリングの打ち替えを行わせて頂いております。
オートンイクシード仕様 なぜ後打ちにしたのか?
「オートンイクシード」は、超寿命シーリング材として知られています。その特性から、「後打ち」工法で採用されることが多いです。
オートンイクシードとは
オートンイクシードは、特殊高耐久ポリマーを配合したシーリング材で、従来のシーリング材の寿命が約10年であるのに対し、30年という驚異的な耐久性を持つとされています。従来のシーリング材に劣化の原因となる可塑剤を使用せず、LSポリマーという新素材を配合することで、長期間にわたって柔軟性を保つことができます。
シーリングの「後打ち」とは
シーリング工事には「先打ち」と「後打ち」の2つの工法があります。
- 先打ち工法: 外壁塗装をする前にシーリング材を充填し、その上から塗装を行う方法です。
- 後打ち工法: 外壁塗装を終えた後に、シーリング材を充填する方法です。
オートンイクシードを「後打ち」するメリット・デメリット
オートンイクシードは後打ちに適しているとされますが、それぞれのメリット・デメリットを理解しておくことが重要です。
メリット - 塗膜のひび割れリスクがない: シーリング材の上に塗料が乗らないため、シーリング材の動きによる塗膜のひび割れや剥がれが発生しません。先打ちでは、シーリング材の柔軟性(伸縮性)と塗料の硬さの違いから、塗膜にひび割れが生じることがあります。
- シーリング本来の機能を発揮: オートンイクシードの高い耐久性と柔軟性が直接外壁に作用するため、シーリング材本来の性能を最大限に活かせます。
デメリット - 紫外線による劣化: シーリング材が直接紫外線や雨風にさらされるため、先打ちに比べて劣化が早まる可能性があります。ただし、オートンイクシードは非常に高い耐候性を持つため、このデメリットは軽減されます。
- 汚れの付着: シーリング材の表面が直接露出するため、ホコリなどが付着しやすいことがあります。
- 色の違い: 外壁の塗膜とシーリング材の色が異なる場合、見た目に違いが出ることがあります。機能性を重視するなら問題ありませんが、見た目を気にする場合は注意が必要です。
オートンイクシードの「後打ち」施工時の注意点 - 下地処理: 既存のシーリングをきれいに撤去し、プライマーを適切に塗布することが重要です。特に、既存シーリングが残っていると接着不良の原因になります。
お客様には、この度もご好評頂き嬉しい限りです(^^♪
この度は、工事に携わらせて頂き誠にありがとうございました!!
M様今後とも末永いお付き合いの程よろしくお願い致します(^_-)-☆
東京都羽村市を拠点に、山梨県・埼玉県・神奈川県と屋根・外壁塗装工事を行っています。
何かお困りごとやご相談等が御座いましたら、株式会社望月建築塗装お問合せ下さい(^^♪